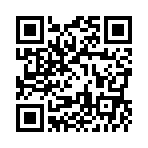2012年05月20日
毒を食らう春の味

お昼に山菜蕎麦を食べた。
スーパーで蕨が売られていたので入手し、グッドタイミングで親から蕗をたくさん炊いたから、と貰ったからだ。
美味しいものには毒がある。特に春を告げる食べ物には毒物が多い。
自然は一見、人に優しいようで全く優しくない。そう思うのは人間の勝手な思い込みだ。
自然に生きるとは生存競争の中で生きて行くことを意味し、すなわち生きるか死ぬかとの鬩ぎ合いである。
時に自分が強くなることで我が身を守り、弱き者は強い者に見付からないよう偽装して騙し、時に我が身に毒を身に付け、食われれば命と引き換えに食った相手も道連れにする。
人間は時としてその毒を持つものですら食べ、旬の味としてきた。
大分県では昔から河豚を食べてきたが、ご存知のように河豚の体内には猛毒のテトロドトキシンを蓄積している。この物質は非常に毒性が強く、青酸カリの850倍以上の毒性を持つ。僅か2mgで成人を死に至らしめる猛毒だ。
しかもテトロドトキシンは安定した自然毒で、どのような加工をしても無毒化できない。
そこで毒の蓄積する部位を取り除いて調理する技術を長い経験から身につけてきたのである。
「河豚は食いたし命は惜しし」
山菜と河豚の毒は関係ないように思うだろ。
今回のお題「蕨」には猛毒が含まれている。
その毒の正体はチアミナーゼ “Thiaminases ”だ。
 人間の必要な栄養素にチアミンがある。
人間の必要な栄養素にチアミンがある。チアミンという名に馴染みは薄いと思う。平たく言うとビタミンB1のことだ。日本では1910年に鈴木梅太郎によって発見されオリザニンと命名された水溶性ビタミンである。
チアミンはアクティブな形になるとチアミンピロリン酸(TPP)としてエネルギー代謝(具体的には糖と脂肪の代謝)の補酵素として機能する。
化学式変化 C12H17N4OS+Cl-.HCl→ C12H19N4O7P2S+
1. アセチル-CoAへのピルビン酸への変換は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼによって触媒される。
2. α-ketogluterateデヒドロゲナーゼにより触媒されるTCA回路のスクシニル-CoAにα-ketogluterateの変換を行う。
3. 分岐鎖α-ケト酸脱水素酵素によってアシルCoAの触媒への分岐鎖α-ケト酸への変換。
4. トランスケトラーゼによって触媒されるペントース - リン酸シャントのアクセプターをアルドースするα-ケト糖から2Cのフラグメントの転送。
このチアミンが不足(40ng/ml以下 ng=10-9g)するといわゆる脚気を発症する。
脚気については以前「カレーライス」でも触れたが、以前は結核と並ぶ国民の二大疾患だった。
この病気は平安時代の頃から度々流行し、精米した白米を食べる上流階級に発生している。江戸時代には一般大衆にも白米食が習慣化して脚気が流行り「江戸患い」と呼ばれた。
蕎麦にはビタミンB1が多く含まれ、脚気の症状改善に役立つということで、江戸では蕎麦が良く食べられるようになった。蕎麦は痩せた土地でも育ち、冷涼な気候を好むことから東日本では良く食べられるが、こういう理由もあった。
 さてチアミナーゼの働きだが、これにはタイプⅠとタイプⅡのフォームがあり、魚類、貝類、シダ類はタイプⅠのチアミナーゼを含んでいる。
さてチアミナーゼの働きだが、これにはタイプⅠとタイプⅡのフォームがあり、魚類、貝類、シダ類はタイプⅠのチアミナーゼを含んでいる。チアミンにチアミナーゼが働き掛けると、チアゾール環を排除するために窒素塩基またはSH-化合物とピリミジンメチレン基を置換することによって作用する。チアミン分子を切断して不活性化し、一旦切断されたチアミン分子は体内で再合成されない。そのためチアミン不足の症状を示すようになる。
軽度であれば体重減少、脱力感を伴う食欲不振、運動麻痺、神経麻痺などの神経障害。重篤になると心不全、浮腫により死に至る。
チアミナーゼを含むものに、蕨、薇のようなシダ植物が多いが、他には淡水魚に多くコイ科の鯉、鮒、金魚(金魚は鮒を観賞用に改良したものだ)、貝類ではマルスダレガイ科の蛤、浅蜊に含まれる。
これらは中毒にならないよう生食を絶対にしないこと。
チアミナーゼ*によるチアミン欠乏症は、1941年にアメリカで毛皮生産用に養殖していたキツネがニューロバチー症候群を起こすことが報告され、淡水魚の内臓にのみチアミナーゼが含まれることが知られるようになった。
*当時はアノイリナーゼと呼ばれていた。以前チアミンがアノイリン、サイアミンと呼ばれていたことに由来する。
蕨や薇は春を代表する山菜ではあるものの、このように不用意に食べると中毒症状をおこすため、適切に処理して食べることが肝要だ。
そうでないと非常にがっかりな春になってしまう確率が高くなる。
因みに蕨は適切に処理しても大量に食べると、発癌物質のプタキロサイド (ptaquiloside)によって体中が大量出血状態になり、次第に骨髄が破壊されて死に至る。
こう聞くと食べたくなってきただろ。
じゃ作り方いくぞ。
蕨の灰汁抜きから行くぞ。
木灰を使う方法と重曹を使う方法があるが、ここでは重曹を使った方法を紹介する。
蕨が全て入るであろう鍋に水を500cc沸かし、重曹を小さじ1/2を溶かす。
重曹とは炭酸水素ナトリウムのことである。化学式はCHNaO3で水酸化ナトリウムに二酸化炭素を反応させて作ったものだ。phはアルカリ性を示す塩基化合物である。
重曹は270℃以上で炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水に分解されるが、水溶液では65℃以上になると急速に分解される。
従って、重曹を溶かした水溶液に蕨を素早く漬ける必要があろう。
因みに鍋の材質はアルミの鍋を避けるべきである。
アルミニウムは酸にも塩基にも反応するため、表面が黒くなるだけでなく穴が開く場合もある。
どんな風に変化するか化学式を書きたくなってきただろ。
6 OH- + 2 Al + 6 H2O → 6 OH- + 2 Al(OH)3 + 3 H2
蕨を炭酸水素ナトリウム水溶液に浸透させたら、一旦煮立ってからすぐに火を止める。長く煮立たせると蕨が溶けたようになるからだ。
後は蕨が液から浮いて露出しないよう皿などを重石にして8時間ほど放置する。よってこの工程は、食べる日の前日就寝前に行うのがよろしい。
翌日、水溶液が茶色に変色しているようであれば灰汁抜きに成功している。
この水溶液を捨て、水に蕨を晒して炭酸水素ナトリウムを抜く作業をする。3回ほど流水で洗って水に晒せば大丈夫だろう。抜き方が甘いと、苦味が残る。
ここから油揚げと蕨の煮浸しを作っていくぞ。
油揚げと蕨の煮浸し
油揚げ…2枚
灰汁抜きした蕨
水…160cc
醤油…大さじ2
砂糖…小さじ1
塩…小さじ1/2
鰹節…5g
油揚げは油抜きして短冊に切っておけ。
鍋に水を沸かし鰹節を入れる。煮えたぎらないよう火は中火。
鰹節は出汁を取ったら他に使うので、網で丁寧にすくいボウルなどに取り出しておく。
調味料を入れて油揚げから炊くぞ。
その間に蕨を切る。
根元の方は硬くて美味しくないので2~3cm切り落とし長さ2等分に切れ。
切った蕨を鍋に入れ一煮立ちしたらすぐに火を止める。ここでは味が馴染めばよい。
適当な器に出してある程度冷めたら、ラップして冷蔵庫へ。冷やすことで細胞膜を破壊した中に味を入れて行こうとしているのだ。
食べる30分前には冷蔵庫から出しておくこと。
つまりこの工程は翌朝起きたら即行うべきである。
鶏の煮物は別の日に豚バラ軟骨の煮込みを作った時の煮汁を薄めた液で炊いた。基本的には蕎麦つゆと似たような味付けにすれば良い。ただし野菜からの旨味は入ってないので味は異なるだろう。
蕎麦つゆ(2倍濃縮)
出汁(昆布と椎茸の戻し汁)…400cc
醤油…100cc
味醂…100cc
鰹節…20g
昆布と椎茸は水から戻し、最低1時間漬けておく。
鍋に戻した汁ごと入れて鰹節も投入。湯が沸く直前に昆布は取り出し、沸騰したら椎茸と鰹節を取り出す。
これらも他に使うので先ほどのボウルに取り出しておく。
醤油と味醂を入れて一煮立ちさせればOK。
もし余りそうならばペットボトルなどで冷蔵庫で保存できるぞ。同量の水で希釈することは忘れるな。
刻みネギや大根おろしの用意ができたら蕎麦を茹でるぞ。
汁は冷めないよう極弱火に掛けておく。
後の説明はいらんだろ。
器に盛って終わりだ。好きなだけ具をのせて食え。
家庭で作ると麺類は意外に手間暇が掛かったりするもんだ。
で、さっきのボウルに取り出した昆布なんかを使って佃煮を作るぞ。
一切、捨てずに味わおうという非常にエコロジーな提案だ。
佃煮
出汁昆布
戻した椎茸
鰹節
胡麻
水…大さじ4
醤油…大さじ2
砂糖…大さじ1
昆布はできるだけ細く切っていく。マッチ棒くらいを目指せ。
椎茸はさすがにマッチ棒とまでは言わないが、できるだけ薄くスライス。
小鍋に調味料を全て入れ、煮立ったところで具材を投入し汁気がなくなるまで焦がさないよう炒り煮する。
このままでも十分日持ちするが、これに練り辛子を入れると更に良いアクセントになるぞ。
さて、今回は危険な食品の味わい方だった。
これらを書いていて、ふと思ったことがある。
原子力発電所のPR館で原子力安全への取り組み説明会が開かれたときの逸話。
中高年数十人を前に、原子力発電所の構造や地震対策、環境対策への取り組み、とりわけ放射性物質が周囲に漏れ出さないようどれだけ厳重に防護されているか、パネルを示しながら説明を行った。
最後に説明を聞いてどう思ったか質問すると、男性からは「今日の説明で、原子力発電所は非常に安全に設計されていると思う」と返ってきた。
ところが1人の女性からは「こんなに厳重に管理しなければならないほど原子力は危険なんですか」と返ってきたという。
全員が、同じ場所で同じ説明を聞いたのに、こんなに反応が違っていたのである。
男女間で考え方が異なる例として引用されていた話なのだが、記憶だけで書いたのでもしかするとディテールが多少異なる可能性はある。
ともかく、だとすれば、この記事を読んだら「そんなに危険なら山菜はもう食べない」だろうし、河豚は「専門家でも間違うことはあるからもう食べない」と思うに違いない。
原子力は原子物理学によって整然と理論が成り立つ分野だが、河豚の毒は何故蓄積されるのかもはっきりとは解っておらず、人間が合成することも困難な物質なのだ。テトロドトキシンそのものは1909年東京帝国大学の田原良純(薬学博士)によって初めて単離に成功しテトロドトキシンと名付けられた。
1964年に名古屋大学の平田正義(天然物化学)、東京大学の津田恭介(有機化学)、ハーバード大学のロバート・バーンズ・ウッドワード(有機化学、ノーベル化学者)の3グルーブがその構造を特定したが、ウッドワードですら合成を断念している。初めて全合成に成功したのは名古屋大学の岸義人博士(ハーバード大教授、米国エーザイ副社長)で1972年のことである。
このように毒の正体は解っていながら人の手に余るものであったが、もちろん河豚はその間も食べられていたのである。
こんな危ないものをありがたがって(簡単には手の出ない値段を払って)食っていた。
もちろん調理する人は免許を持ち、修行をつんだ料理人だが、そんな人でも失敗や間違いはある、そういう僅かなリスクも避けようと思ったら、この世に食べられるものは全くなくなってしまうだろうな。
薬だって副作用が危ないと言って、これも使えなくなる。
アレも危ない、コレも危ないと言っていたのでは生きて行けなくなるぞ。
この世にリスクのないものなんかないはずだ。
オレはこう思う。
リスクよりメリットが大きく上回るからこそ、人類はリスクを乗り越えてきたと。
薬は自然にあるものが特定の効能を持ち、その働きに化学のメスを入れることで解明して開発したものだ。そのために実験を繰り返し副作用が出ない薬を開発してきた。
少なくとも体質に影響を受けたり、不安定な不純物を含んだりする漢方薬よりはずっと安全だ。
科学に理由のない不安を感じ、自然のものには無抵抗に安全と思うのは、単に思い込みか偏見でしかない。
人類の歴史は自然を克服する歴史だ。100年前でもとても自然と呼べるようなシロモノじゃない。
「自然」と呼べるものは2000年くらい遡れば言えなくもない。
大自然はちっぽけな我々に情け容赦なく襲い掛かってくるものだ。これを人間は火を使い、道具を使い、科学によって恐ろしくないものにしてきた。征服することによって、安心して暮らせる人間社会を構築したのだ。
多くの人が言う自然とは「人の手が加わった自然」であり「荒れ狂う自然」ではない。
ノスタルジックとワイルドは全く異なるものだ、勘違いするな。
参考資料
高木兼寛とその批判者たち~脚気の原因について議論されたわが国最初の医学論争~
フグ毒テトロドトキシンの全合成 古くて新しい天然物合成の魅力と重要性
コーネル大学動物科学科 家畜に有毒な植物データベース<チアミン>
季節外れの山菜は塩蔵されたもの。塩蔵するとチアミナーゼが失活することが知られている。
河豚の卵巣には致死量のテトロドトキシンが含まれる。しかし石川県では卵巣を糠漬けにして無毒化する特産品がある。この方法でなぜ無毒になるのかわかっておらず、経験によるものだそうだ。
ただし出荷するに当たっては、社長自ら体を張った毒見をして時折中り、3年ないし5年おきに社長が交代する
ようなことはなくマウス実験して出荷されるそうだ。
木灰を使う方法と重曹を使う方法があるが、ここでは重曹を使った方法を紹介する。
蕨が全て入るであろう鍋に水を500cc沸かし、重曹を小さじ1/2を溶かす。
重曹とは炭酸水素ナトリウムのことである。化学式はCHNaO3で水酸化ナトリウムに二酸化炭素を反応させて作ったものだ。phはアルカリ性を示す塩基化合物である。
重曹は270℃以上で炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水に分解されるが、水溶液では65℃以上になると急速に分解される。
従って、重曹を溶かした水溶液に蕨を素早く漬ける必要があろう。
因みに鍋の材質はアルミの鍋を避けるべきである。
アルミニウムは酸にも塩基にも反応するため、表面が黒くなるだけでなく穴が開く場合もある。
どんな風に変化するか化学式を書きたくなってきただろ。
6 OH- + 2 Al + 6 H2O → 6 OH- + 2 Al(OH)3 + 3 H2
蕨を炭酸水素ナトリウム水溶液に浸透させたら、一旦煮立ってからすぐに火を止める。長く煮立たせると蕨が溶けたようになるからだ。
後は蕨が液から浮いて露出しないよう皿などを重石にして8時間ほど放置する。よってこの工程は、食べる日の前日就寝前に行うのがよろしい。
翌日、水溶液が茶色に変色しているようであれば灰汁抜きに成功している。
この水溶液を捨て、水に蕨を晒して炭酸水素ナトリウムを抜く作業をする。3回ほど流水で洗って水に晒せば大丈夫だろう。抜き方が甘いと、苦味が残る。
ここから油揚げと蕨の煮浸しを作っていくぞ。
油揚げと蕨の煮浸し
油揚げ…2枚
灰汁抜きした蕨
水…160cc
醤油…大さじ2
砂糖…小さじ1
塩…小さじ1/2
鰹節…5g
油揚げは油抜きして短冊に切っておけ。
鍋に水を沸かし鰹節を入れる。煮えたぎらないよう火は中火。
鰹節は出汁を取ったら他に使うので、網で丁寧にすくいボウルなどに取り出しておく。
調味料を入れて油揚げから炊くぞ。
その間に蕨を切る。
根元の方は硬くて美味しくないので2~3cm切り落とし長さ2等分に切れ。
切った蕨を鍋に入れ一煮立ちしたらすぐに火を止める。ここでは味が馴染めばよい。
適当な器に出してある程度冷めたら、ラップして冷蔵庫へ。冷やすことで細胞膜を破壊した中に味を入れて行こうとしているのだ。
食べる30分前には冷蔵庫から出しておくこと。
つまりこの工程は翌朝起きたら即行うべきである。
鶏の煮物は別の日に豚バラ軟骨の煮込みを作った時の煮汁を薄めた液で炊いた。基本的には蕎麦つゆと似たような味付けにすれば良い。ただし野菜からの旨味は入ってないので味は異なるだろう。
蕎麦つゆ(2倍濃縮)
出汁(昆布と椎茸の戻し汁)…400cc
醤油…100cc
味醂…100cc
鰹節…20g
昆布と椎茸は水から戻し、最低1時間漬けておく。
鍋に戻した汁ごと入れて鰹節も投入。湯が沸く直前に昆布は取り出し、沸騰したら椎茸と鰹節を取り出す。
これらも他に使うので先ほどのボウルに取り出しておく。
醤油と味醂を入れて一煮立ちさせればOK。
もし余りそうならばペットボトルなどで冷蔵庫で保存できるぞ。同量の水で希釈することは忘れるな。
刻みネギや大根おろしの用意ができたら蕎麦を茹でるぞ。
汁は冷めないよう極弱火に掛けておく。
後の説明はいらんだろ。
器に盛って終わりだ。好きなだけ具をのせて食え。
家庭で作ると麺類は意外に手間暇が掛かったりするもんだ。
で、さっきのボウルに取り出した昆布なんかを使って佃煮を作るぞ。
一切、捨てずに味わおうという非常にエコロジーな提案だ。
佃煮
出汁昆布
戻した椎茸
鰹節
胡麻
水…大さじ4
醤油…大さじ2
砂糖…大さじ1
昆布はできるだけ細く切っていく。マッチ棒くらいを目指せ。
椎茸はさすがにマッチ棒とまでは言わないが、できるだけ薄くスライス。
小鍋に調味料を全て入れ、煮立ったところで具材を投入し汁気がなくなるまで焦がさないよう炒り煮する。
このままでも十分日持ちするが、これに練り辛子を入れると更に良いアクセントになるぞ。
さて、今回は危険な食品の味わい方だった。
これらを書いていて、ふと思ったことがある。
原子力発電所のPR館で原子力安全への取り組み説明会が開かれたときの逸話。
中高年数十人を前に、原子力発電所の構造や地震対策、環境対策への取り組み、とりわけ放射性物質が周囲に漏れ出さないようどれだけ厳重に防護されているか、パネルを示しながら説明を行った。
最後に説明を聞いてどう思ったか質問すると、男性からは「今日の説明で、原子力発電所は非常に安全に設計されていると思う」と返ってきた。
ところが1人の女性からは「こんなに厳重に管理しなければならないほど原子力は危険なんですか」と返ってきたという。
全員が、同じ場所で同じ説明を聞いたのに、こんなに反応が違っていたのである。
男女間で考え方が異なる例として引用されていた話なのだが、記憶だけで書いたのでもしかするとディテールが多少異なる可能性はある。
ともかく、だとすれば、この記事を読んだら「そんなに危険なら山菜はもう食べない」だろうし、河豚は「専門家でも間違うことはあるからもう食べない」と思うに違いない。
原子力は原子物理学によって整然と理論が成り立つ分野だが、河豚の毒は何故蓄積されるのかもはっきりとは解っておらず、人間が合成することも困難な物質なのだ。テトロドトキシンそのものは1909年東京帝国大学の田原良純(薬学博士)によって初めて単離に成功しテトロドトキシンと名付けられた。
1964年に名古屋大学の平田正義(天然物化学)、東京大学の津田恭介(有機化学)、ハーバード大学のロバート・バーンズ・ウッドワード(有機化学、ノーベル化学者)の3グルーブがその構造を特定したが、ウッドワードですら合成を断念している。初めて全合成に成功したのは名古屋大学の岸義人博士(ハーバード大教授、米国エーザイ副社長)で1972年のことである。
このように毒の正体は解っていながら人の手に余るものであったが、もちろん河豚はその間も食べられていたのである。
こんな危ないものをありがたがって(簡単には手の出ない値段を払って)食っていた。
もちろん調理する人は免許を持ち、修行をつんだ料理人だが、そんな人でも失敗や間違いはある、そういう僅かなリスクも避けようと思ったら、この世に食べられるものは全くなくなってしまうだろうな。
薬だって副作用が危ないと言って、これも使えなくなる。
アレも危ない、コレも危ないと言っていたのでは生きて行けなくなるぞ。
この世にリスクのないものなんかないはずだ。
オレはこう思う。
リスクよりメリットが大きく上回るからこそ、人類はリスクを乗り越えてきたと。
薬は自然にあるものが特定の効能を持ち、その働きに化学のメスを入れることで解明して開発したものだ。そのために実験を繰り返し副作用が出ない薬を開発してきた。
少なくとも体質に影響を受けたり、不安定な不純物を含んだりする漢方薬よりはずっと安全だ。
科学に理由のない不安を感じ、自然のものには無抵抗に安全と思うのは、単に思い込みか偏見でしかない。
人類の歴史は自然を克服する歴史だ。100年前でもとても自然と呼べるようなシロモノじゃない。
「自然」と呼べるものは2000年くらい遡れば言えなくもない。
大自然はちっぽけな我々に情け容赦なく襲い掛かってくるものだ。これを人間は火を使い、道具を使い、科学によって恐ろしくないものにしてきた。征服することによって、安心して暮らせる人間社会を構築したのだ。
多くの人が言う自然とは「人の手が加わった自然」であり「荒れ狂う自然」ではない。
ノスタルジックとワイルドは全く異なるものだ、勘違いするな。
参考資料
高木兼寛とその批判者たち~脚気の原因について議論されたわが国最初の医学論争~
フグ毒テトロドトキシンの全合成 古くて新しい天然物合成の魅力と重要性
コーネル大学動物科学科 家畜に有毒な植物データベース<チアミン>
季節外れの山菜は塩蔵されたもの。塩蔵するとチアミナーゼが失活することが知られている。
河豚の卵巣には致死量のテトロドトキシンが含まれる。しかし石川県では卵巣を糠漬けにして無毒化する特産品がある。この方法でなぜ無毒になるのかわかっておらず、経験によるものだそうだ。
ただし出荷するに当たっては、社長自ら体を張った毒見をして時折中り、3年ないし5年おきに社長が交代する
ようなことはなくマウス実験して出荷されるそうだ。
Posted by *clear* at 14:14│Comments(0)
│おいちーよ♪