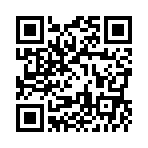2012年07月30日
土用なので格安に鰻を食べてみた

土用の丑の日に鰻が店頭に並んでいるのであるが、とても手が出るような値段ではない。
ど~せ、ウナギなんか数年口にした憶えはないけどね。
3年連続でシラスウナギが不漁で、国産はおろか中国や台湾でも稚魚不足による価格高騰が続いている。養殖でさえ、もはや庶民には高嶺の花、と言える食べ物となった感がある。
江戸時代から、鰻は高いものだったらしいが、大分のような田舎では、夏ともなれば、川に行けば普通に捕れる魚だった。子供の頃は、台風の後には、田に水を引く水路に、ナマズやウナギが流れ込み、大量に捕れることも多かった。
今では考えられない時代だ。
さて、ウナギを土用の丑の日に食べるようになったのは、江戸末期だと言われている。
ウナギが売れずに困っていたところ、それを平賀源内が「夏の暑気払い」として売り出したらどうか、とアドバイスしたのが始まりだとする説がある。
しかし、江戸は大規模な干拓を行った際に、ウナギが棲み付きこれが食べられるようになったのが始まりのようだ。最初は単なる塩焼きだったが、タレに漬けて焼く方法は江戸中期である。
ウナギには豊富な栄養素がバランス良く含まれており、不足するのはビタミンCくらいだ。総合栄養食として評価できる食品のひとつである。
しかし、近年の価格を鑑みれば、その価格に見合うとも思われず、肉食が禁忌だった昔からすれば、遥かに動物性蛋白質の種類は増えており、ウナギでなくともリーズナブルに栄養の補給は可能な時代である。
ウナギを夏に食べたい、という衝動は一種の日本人が持っている風物詩への情緒だと思われる。
ならば、ということで、生臭が禁忌だった僧侶の知恵を借ろうというのが、今回のお題である。
坊さんも人の子。やはりウナギは食いたかったのだろう。
これならば、恐らく本物のウナギの10分の1以下の予算で、ウナギを食べた気分を味わえる。
じゃ、作り方いくぞ。
鰻もどき丼
<鰻本体>
豆腐…1丁(400g)
長芋…100g
牛蒡…1/4本
塩…ひとつまみ
片栗粉…適宜
味付け海苔…9枚程度
揚げ油…適宜
<タレ>
出汁汁…120cc
醤油…大さじ2.5
砂糖…大さじ2
味醂…大さじ1
酒…大さじ1
水溶き片栗粉…適宜
鰻もどきの材料の役割を説明しておこう。
豆腐は言うまでもなく「身」の部分。長芋はふっくら感の演出。牛蒡は泥臭さと小骨。海苔は皮の部分である。
今回作った鰻もどきは、関東の蒸篭で蒸して蒲焼にしたものに酷似する。
西日本だと、直接蒲焼にする関西のスタイルが馴染み深い。このような食感が欲しい場合は、材料を工夫必要があるだろう。特に、関西以西のは歯応えがある物なので、魚のすり身や卵を加えないとあの感じにならないように思われる。
さて、材料の仕込から。
豆腐は水を切るのだが、キッチリ水を切る必要がある。冷蔵庫で重しをして一晩以上水を切るか、レンジで加熱して水を切るかどちらかを選択することになる。どちらでやっても構わないが、水はできるだけ出し切ってしまう。
牛蒡はたわしで皮を落とし、長芋はピーラーで皮を剥く。
どちらも摩り下ろせ。
すり鉢で豆腐、牛蒡、長芋を合わせて行く。豆腐の形が残らない方が、よりリアルな鰻になる。
すり鉢が面倒なら、フードプロセッサーで合わせる方法もあるが、容量がそれなりに必要。
この辺は、手持ちの機器によるだろう。
塩をひとつまみ加え、粘りが足りない場合は片栗粉を加えて調整する。
できたタネを海苔に乗せて整形する。
ナイフ状のものであれば何でも構わないが、鰻の形に似せて整形すると、ホンモノ感が上がるだけでなく、タレの絡みも良くなる。
欲を言えば、今回のは関東風だから背開きをイメージすれば尚良いだろう。
注意すべきは、比較的均等に厚さを整形することだ。油で揚げるのは、厚さを考えればわかるが、あっという間に揚がってしまう。従って、厚さにムラがあると焦げやすくなる。
また、箸を使うより網を使った方が、不用意に崩してしまうリスクも少ない。
タレは、本来なら鰻の骨を入れて作るそうだが、ウナギもどきに本物を入れるのは邪道に思える。
あくまで「それらしさ」を他のもので補った方が、より趣旨に沿った達成感を味わえるに違いない。
材料を鍋に煮立てて煮詰め、片栗粉で適度にとろみを出したら、丼によそって出来上がり。
好みで粉山椒を振っても良い。
食べた感想は、うん「ウナギだ」
蒸したふっくら柔らかい鰻の食感にそっくりで、ちょっと笑ってしまう。うんうん、そっくりだ。
油で揚げてあるので、本物ほど濃厚感はないにしても、アッサリ過ぎでがっかりするほどニセモノな感じがしない。昔の人の知恵、というよりバイタリティには凄いものがある。
ひょっとして、鰻の味はほとんど「タレ」で決まるんじゃないか、などと貧乏人の舌で考えてみる。
今年は鰻が高過ぎて売れないんだろう。アナゴが売られていたり、本業の鰻屋で豚の蒲焼が提供されたりと、苦心している。それを横目にウナギもどき、というのもオツだな。
欲を言うと、もう少し簡単に作れりゃ文句ないんだが。
水産庁では5年後を目処に、鰻の完全養殖を試みる計画を建てた。
養殖ウナギから孵化させて、シラスウナギを現在の600匹から1万匹まで増産する技術の確立を目指す。
何しろ、産卵する場所がマリアナ海溝だというのがわかったのは10年ほど前のことだ。稚魚が何を食べているのかもハッキリしていない。良く知っている魚でありながら、その生態は謎だらけの鰻。
5年後、果たして本物の鰻は食べられるのだろうか。
さて、うなぎの代替としてアナゴが注目されているのだが、実は食品的には脂の量が少なくなればアナゴと見分けがつかないらしい。料理人ですら間違えるんだから、果たしてウナギの有り難味とは。
<鰻本体>
豆腐…1丁(400g)
長芋…100g
牛蒡…1/4本
塩…ひとつまみ
片栗粉…適宜
味付け海苔…9枚程度
揚げ油…適宜
<タレ>
出汁汁…120cc
醤油…大さじ2.5
砂糖…大さじ2
味醂…大さじ1
酒…大さじ1
水溶き片栗粉…適宜
鰻もどきの材料の役割を説明しておこう。
豆腐は言うまでもなく「身」の部分。長芋はふっくら感の演出。牛蒡は泥臭さと小骨。海苔は皮の部分である。
今回作った鰻もどきは、関東の蒸篭で蒸して蒲焼にしたものに酷似する。
西日本だと、直接蒲焼にする関西のスタイルが馴染み深い。このような食感が欲しい場合は、材料を工夫必要があるだろう。特に、関西以西のは歯応えがある物なので、魚のすり身や卵を加えないとあの感じにならないように思われる。
さて、材料の仕込から。
豆腐は水を切るのだが、キッチリ水を切る必要がある。冷蔵庫で重しをして一晩以上水を切るか、レンジで加熱して水を切るかどちらかを選択することになる。どちらでやっても構わないが、水はできるだけ出し切ってしまう。
牛蒡はたわしで皮を落とし、長芋はピーラーで皮を剥く。
どちらも摩り下ろせ。
すり鉢で豆腐、牛蒡、長芋を合わせて行く。豆腐の形が残らない方が、よりリアルな鰻になる。
すり鉢が面倒なら、フードプロセッサーで合わせる方法もあるが、容量がそれなりに必要。
この辺は、手持ちの機器によるだろう。
塩をひとつまみ加え、粘りが足りない場合は片栗粉を加えて調整する。
できたタネを海苔に乗せて整形する。
ナイフ状のものであれば何でも構わないが、鰻の形に似せて整形すると、ホンモノ感が上がるだけでなく、タレの絡みも良くなる。
欲を言えば、今回のは関東風だから背開きをイメージすれば尚良いだろう。
注意すべきは、比較的均等に厚さを整形することだ。油で揚げるのは、厚さを考えればわかるが、あっという間に揚がってしまう。従って、厚さにムラがあると焦げやすくなる。
また、箸を使うより網を使った方が、不用意に崩してしまうリスクも少ない。
タレは、本来なら鰻の骨を入れて作るそうだが、ウナギもどきに本物を入れるのは邪道に思える。
あくまで「それらしさ」を他のもので補った方が、より趣旨に沿った達成感を味わえるに違いない。
材料を鍋に煮立てて煮詰め、片栗粉で適度にとろみを出したら、丼によそって出来上がり。
好みで粉山椒を振っても良い。
食べた感想は、うん「ウナギだ」
蒸したふっくら柔らかい鰻の食感にそっくりで、ちょっと笑ってしまう。うんうん、そっくりだ。
油で揚げてあるので、本物ほど濃厚感はないにしても、アッサリ過ぎでがっかりするほどニセモノな感じがしない。昔の人の知恵、というよりバイタリティには凄いものがある。
ひょっとして、鰻の味はほとんど「タレ」で決まるんじゃないか、などと貧乏人の舌で考えてみる。
今年は鰻が高過ぎて売れないんだろう。アナゴが売られていたり、本業の鰻屋で豚の蒲焼が提供されたりと、苦心している。それを横目にウナギもどき、というのもオツだな。
欲を言うと、もう少し簡単に作れりゃ文句ないんだが。
水産庁では5年後を目処に、鰻の完全養殖を試みる計画を建てた。
養殖ウナギから孵化させて、シラスウナギを現在の600匹から1万匹まで増産する技術の確立を目指す。
何しろ、産卵する場所がマリアナ海溝だというのがわかったのは10年ほど前のことだ。稚魚が何を食べているのかもハッキリしていない。良く知っている魚でありながら、その生態は謎だらけの鰻。
5年後、果たして本物の鰻は食べられるのだろうか。
さて、うなぎの代替としてアナゴが注目されているのだが、実は食品的には脂の量が少なくなればアナゴと見分けがつかないらしい。料理人ですら間違えるんだから、果たしてウナギの有り難味とは。
Posted by *clear* at 13:26│Comments(0)
│おいちーよ♪