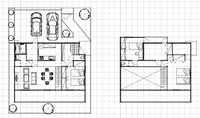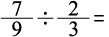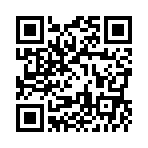2011年07月03日
問題!
高校入試問題の一例です。
理科の設問6、配点は各2点の合計12点。
次のような手順で実験を行い、水または水溶液の温度が時間の経過とともにどう変化するかを調べた。下の図は経過時間と温度との関係をグラフに表したものである。次の問いから問4に答えよ。なお、水は状態によって氷、水、水蒸気というように呼び方が異なるが、ここでは水とはH2Oという分子式で表される物質をさす。
実験
手順1 –10度の氷200gをビーカーに入れてゆっくり加熱した。
手順2 水が60度に達した段階で70gのミョウバンを加え、完全に溶かした。その後5分間は温度を保った。
手順3 その後ビーカー全体を冷却した。
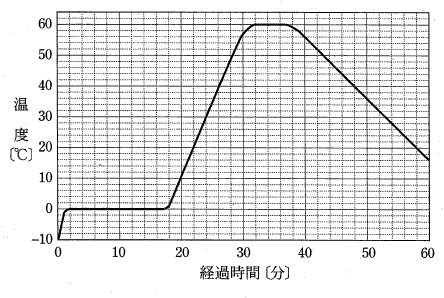
問1 初めに入れた水(固体)は、加熱を始めて5分後および20分後にどのような状態になっているか。
問2 次の文章は、水が固体から液体に変化するときの、体積と質量の変化に関して述べたものである。空欄1、2に当てはまる適当な語を書け。
水は身近でありふれた物質であるが、他の物質とは異なる特徴が多い。水は固体から液体に変化するとき、体積は(1)。また、質量は(2)。このことは、コップの中の氷が水に浮く原因である。
問3 下の図は、100gの水に飽和するまで溶けるミョウバンの質量(ミョウバンの溶解度)が水の温度によってどのように変化するかグラフに表したものである。水100gにミョウバン24gを溶解させるためには、水の温度を何度以上にしなければならないか。
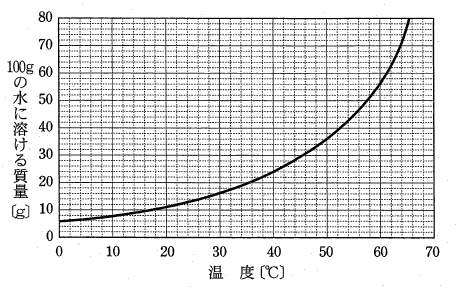
問4 先の-10度の氷から始めた実験でできるミョウバン水溶液が飽和水溶液になったのはいつか。
できた人は手を挙げて(笑)
よく読んで落ち着いて答えれば、そう難しい問題ではないのですが、ちょっとしたヒッカケ問題があるのでレポートしてみました。
因みに設問の答えは選択方式なのですが、長くなるので記述式に問題を変更しています。別に意地悪してるんじゃないんですよ。
問1は5分後では「液体と固体が混ざった状態」20分後は「液体の状態」に近い答えだったら正解。
グラフの約1分から18分までの間で温度変化がありません。5分後が問うているのは「潜熱」です。沸点に達した固体が溶解するとき温度変化のない状態になります。水は潜熱が大きい物質です。
20分後では温度上昇が見られ潜熱の状態から抜け出ていますから「液体」となります。
問2は1が「減少する」2が「変化しない」
液体は温度が下がると密度が大きくなるのに、水は3.98度で最も密度が高くなるため氷になっても質量は変わりません。体積は水より9%大きくなります。
問3はグラフを素直に読めば求められる問題です。一メモリは2gですから24gのラインが交わるところをみると40度になります。
問4がちょっと曲者です。
問3で使ったグラフから温度を読み取るのですが、まず最初のヒッカケが水の量です。実験で溶かしたミョウバンは70gですからグラフの70gを読みそうになります。
実験で使った水は200gですから、そう「35g」を見なければなりません。それで見ると大体49度が飽和水溶液になる温度のようです。
それで実験のグラフの49度になる時間を見ます。28分後辺りが49度になっているのでこの時間と思いそうですが、ここもヒッカケです。
実験手順を読み直すとこの時間にはミョウバンが溶かされていません。入れたのは60度になってからなので、それ以前の時間は無視して良いということになります。飽和点に達するのは冷却を始めてからだと分かるので、それを読むと加熱開始から43分後くらいでしょうか。
問題ではいくつかある選択から最も適当なものを選べ、なので最も近い数値である44分後が正解。
全体的に水の特徴を問う内容ですが、問4は文章読解能力もみているような感がありました。他の教科の問題でも比較的設問の文章が長く、加えて答えを導き出すまでのプロセスを重要視しているようでした。
僕もできたから偉そうに書いてるんですが、実は問4で温度上昇中のところを読みそうになりました。僕も経験してきた道ですけど、受験生も大変だな。
今、息子と一緒になって解いてみると結構おもしろい。
どうしてあの時おもしろいって思わなかったんだろう?
因みに大学入試の問題はパスです。
だって工業系だから数学と物理以外は文系普通科に敵うわけないっス。
Posted by *clear* at 15:04│Comments(2)
│受験・進路
この記事へのコメント
中学生の理数の問題って結構面白いよね。
僕の部署は理系の学者みたいな連中が多いので、
難問を持っていくとみんなメッチャ食いついて解き始めるから面白いよ。
僕の部署は理系の学者みたいな連中が多いので、
難問を持っていくとみんなメッチャ食いついて解き始めるから面白いよ。
Posted by さうるばーと at 2011年07月03日 22:58
at 2011年07月03日 22:58
 at 2011年07月03日 22:58
at 2011年07月03日 22:58>さうるばーとさん
普通は基礎的な定理を組み合わせて解く応用問題が多い中、
こういう時系列まで理解を求める問題は珍しいですね。
ここの問題は英語も長文だったし、
とにかく早く文章の骨子を見抜く力が重要視されているようです。
一番気掛かりなのは「プレッシャー」の中で、
落ち着いてそれを判断できるかです。
彼の学力なら十分受かるレベルですが、
本番で発揮できない生徒はたくさんいますからね。
普通は基礎的な定理を組み合わせて解く応用問題が多い中、
こういう時系列まで理解を求める問題は珍しいですね。
ここの問題は英語も長文だったし、
とにかく早く文章の骨子を見抜く力が重要視されているようです。
一番気掛かりなのは「プレッシャー」の中で、
落ち着いてそれを判断できるかです。
彼の学力なら十分受かるレベルですが、
本番で発揮できない生徒はたくさんいますからね。
Posted by *clear* at 2011年07月04日 12:16