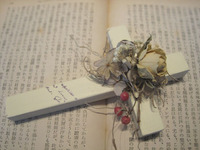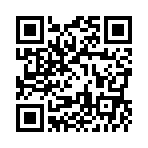2012年06月09日
ジネッタ
写真に写っているスーパーセブンは言うまでもなく有名な車両だが、一緒に並んで写っていた小さな水色のクルマをご存知だろうか?


クルマ好きは勿論即答だと思われる。
そうジネッタだ。イギリスには数多くのバックヤードビルダーが存在しており、ロータスもかつてはそのひとつだった。ジネッタもそんなメーカーで、現在もバックヤードビルダーの要素を色濃く残したメーカーだ。


ジネッタの歴史は、1957年にイギリスのサーフォーク州で建築業を営んでいたクルマ好きのウォークレット四兄弟、ダグラス、トレバー、ボブ、アイバーによって、中古のウーズレイ・ホーネットを改造したG1というレーサーが作られたことによって始まる。このレーサーは彼等が地元のスネッタートン・サーキットをはじめ当時各地で行われていた草レースに出場するためのレーサーだった。しかし試運転の際、家を出たところでクラッシュしてスクラップになってしまう。
しかしこの事故が彼等に火をつけたのか、すぐに次のマシンの製作に取り掛かり完成させたG2は、25mm鋼管スペースフレームにフォードの1.1リッターエンジンを載せ、高い評価を得ることになる。
本来は彼等がレースに出るために製作されたレーサーだったが、近所のクルマ好き達に製作の注文を受けるのである。
ウォークレット兄弟は半完成品のキットカーとしてG2を156ポンドの値段で販売した。当事、イギリスでは自動車に50%もの物品税が掛けられていたが、キットカーはこの消費税が課税されなかったことから、キットカーは「どうしてもクルマを持ちたい、運転したい」と考えるクルマ好きの庶民に人気が高かった。このレーサーの成功がバックヤードビルダーとしての道を決定付け、彼等が自動車メーカーとして進む決心をさせる。つまり「ジネッタカーズ社」の誕生だ。
1960年にはG2の改良型でFRP製のボディーを採用したG3が登場、翌年の1961年にはジネッタの最大のヒット作であるジネッタG4がロンドン・レーシングカーショーでデビューする。
G4はラウンドチューブのスペースフレームにアイバーがデザインしたFRPのボディーを被せた小さなスポーツカーで、デビューと同時にサーキットにも姿を現し、話題を集める。
サスペンションはフロントが上下Aアームによるダブルウイッシュポーン+コイル。リヤはフォード・アングリアから流用したライブアクスルをトレーリングアームとAブラケットで固定+コイルというレイアウトで、重量は完成車で419Kgだった。ボディサイズは3350×1422×685(フロントウインドまで含めると923mm)ホイールベース2030mm、トレッドは前後共に1168mm。かなり小さい。
幅だけは広いが、まぁ昔の軽四並みの大きさで異常に低い車体を想像すればいいと思う。
G4には当初クライマックス750ccが搭載される予定だったが、このエンジンが多くのバックオーダーをかかえて入手が困難な為、しかたなくフォード・アングリアの105E・977cc・OHVエンジンが搭載される。
完成車は697ポンド、キットで499ポンドという価格で販売され、16ポンドのオプション料金でフォード109E・1340ccエンジンも選べた。
時を同じくしてウォークレット兄弟はそれまでの建築業を完全に廃業し、エセックスに工場を設立している。恐らく、このG4が成功すると確信していたのだろう。
さて当事のキットカーとはどんな内容だったのだろうか。G4では以下のような内容でオーナーの元に届けられていたようだ。
1エンジンとスプリング、ショックまでが組まれた完成シャシー
2インパネとメーター類
3スイッチ類、シート
4オースチン・スプライトから流用したフロントガラス
5ホイール、タイヤ5個
6ボディパネル
何となく「ラジコン」を連想した。
この内容ならやる気と場所さえあれば作れそうだ。クルマも小さいので、さほど場所は取らなかっただろう。「小さく軽い」のはキットカーでは個人が趣味で作る裏庭サイズとして必須だったと思われる。
2年後の1963年、G4は多くの部分に改良を受けシリーズ2へと発展する。
フレームはチューブラーパイプからスクウェアパイプで構成されるようになり、エンジンペイのサイドシルが下げられフロントサスペンションもウイッシユポーンのロアアームのピポット位置を16mmずつ外側に出しスプリングのストロークを増している。フロントディスクブレーキの採用もこの時からだ。
最も変更を受けたのはボディーで、リヤのテールフィンを廃止し、いわゆるスラブタイプと呼ばれる、絞り込んだリヤスタイルとなりトランクルームが拡大される(全長は3547mmに伸びる)
多分、日本で一番有名なボディーがこのモデルだ。
そして、合わせガラスのフロントウインドとパースペックスと呼ばれる樹脂製のサイド・リヤウインドを持つ脱着可能なハードトップもオプションで用意された。因みにG4にはドアノブがない。オープンモデルは問題ないが、ハードトップではサイドのウインドウに開けられた穴から腕を突っ込み手探りで内側のリリースハンドルを探るワケだ。知らない人はどうやってドアを開けるかすらわからない(笑)
まだエンジンは基本的に997ccのフォード105Eだった。というのも、当時の国際レース規定で市販車部門は同一エンジンを登載したクルマが100台以上作られていることと定められていたからだ。そして、9月にようやくG4は100台以上の生産によるホモロゲーションが認められる。その後、エンジンのラインナップも増やされフォード113E/1198cc、116E/1498ccエンジンも選択できるようになるのだ。ちなみに116Eを積んだモデルは、当初G5と名付けられ発売されたが、市場ではG4のハイパワー版と受けとめられ、G5の名前が全く定着せず、結局メーカー自らG4-1500とモデル名を変えた経緯がある。まぁ東京ドームの“ビッグエッグ”も定着しなかったしね(笑)
この時期、更に本人の希望に応じてコルチナの112Eやロータスツインカムも選択できるようになる。
そして64年に登場した、G4シリーズ2をベースにリヤのサスペンションをフロントと同じダブルウイシュボーンに変え、4輪独立とし4輪ディスクプレーキを採用したG4Rというレーシングモデルがある。
今回見掛けたG4はこのG4Rだ。

当時、草レースに参加していたドライバー達から同じ105Eを載むロータスセプンよりも戦闘力が高いと評判だった。
G4・G4Rはこの後、イギリス国内レースで多くの戦債を残している。
特に64年はそのピークと言え、ワークスドライバーのクリス・ミークは自分で組み立てたG4にコスワースのカムシャフトを組み込んだフォード製1650ccのOHVエンジンを搭載し、lシーズンに8回の優勝・6回の2位を獲得するなどの戦績を収めている。更にG1のころからホームグラウンドであったスネッタートン・サーキットでは2000cc・180馬力のポルシェ904が樹立したコースレコードもあっさりと塗り替えてしまっている。
レースでの戦績はすぐに人々の話題となり、市販車も順調に販売を伸ばした。当時のイギリスをはじめヨーロッパではレースの戦績が市販車の販売に大きく影響していた。それはワリと最近までの傾向のようだ。例えばAlfa Romeo155も最初は全く売れなかったが、DTMやBTCCで活躍をはじめた途端売れるようになっている。
G4も最終的に500台以上の生産が記録されている。この成功によりジネッタカーズ社は経営安定の基盤を築くことができた。
G4はエンジンやシャシーを改良しながら様々なバリエーションが発売されている。

1966年、いよいよG4に代わるレーサーとしてG12を市場に送りだす。
G12は純粋にサーキットレースでの使用を目的として開発され、G4と共通なのはフロントスタイルと鋼管フレームにFRPボディーを被せている事くらいで中身はまったくの別物。ミッドシップ・レイアウトを採用したボディサイズは3500×1550mm×1050mmとG4にくらべ若干大きくなった。
サスペンションはフロントがトライアンフスピットファイアから流用したダブルウイッシユポーン/コイルにスタビライザー。リヤは長いダブルラジアスアームで位置決めされた逆A型ロアウイッシュボーンとトランスバーリンク/コイルにアジャスタブルスタビライザーを採用した独立懸架を採用。ブレーキもスピットファイアから流用したガーリング製4輪ディスクが奢られている。流用とはいえ、スピットファイアは車体重量が800kgに対してG12は560kgで240kgも軽いから十分な制動力だった。ドライバーの背後に完全にミッドシップで縦置きされたエンジンは、相変わらずG4と同じ105E(39PS/5000rpm)が標準だったが、実際のレースではG12はスペシャルGTクラス/1150cc以下にエントリーされるのでコスワースSCAというフォード105Eをベースに5ベアリング&SOHC化したフォーミュラー2用エンジン(115PS/8750rpm)を搭載するのがほとんどだったという。
ミッションはヒューランドMk-4の5速にLSDを組み合わせ、67年からは1498ccのロータスツインカムをチューンした1594ccのコスワースMk-8が搭載されている。
G12は9月のシルバーストーンのデビュー戦でワークスドライバーのウイリー・グリーンによってラップレコードを記録。続いてホームグランドのスネッタートンではクラス優勝を果たす。
また翌年にはブランズハッチで7リッターのシェルビー・コブラ、4・7リッターフォードGT40という強敵を打ち破るなど数々の輝かしい戦績を収め、以降、ロータスエラン、TVRといった上級クラスのクルマを相手に活躍し1150cc以下クラスでは無敵を誇った。
レースに出場し勝つ事を命題とされたG12は、キットカーではなくコンプリートカーだけが販売され、その価格は1200ポンドだった。オリジナルのG12は50台弱の生産が記録されている。
しかし、純粋にサーキットを走るために生を受けたG12は公道を走るにはあまりにスパルタン過ぎていた。特に複雑なシャシーは手間とコストが嵩み生産性を大きく損なっていた。実のところ、ロータスもスーパーセブンシリーズで同じジレンマに陥っていた。それがスーパーセブンの販売停止という事態に繋がったのだが、ライバルであるジネッタも同様だったとは何とも奇遇な現象である。
こういった反省から、企業としてもっと生産性の高いスポーツカーを作るべきだ、として登場したのがG15である。生産台数は800台を数え、後にも先にもこれを超えるヒット作は生まれなかった。
G4は67年によりラグジュアリーに振ったモデルを登場させるが、市場からの反応はイマイチで69年に生産を終了する。
68年にはG12の発展型であるG16が登場したことで実質的にG12の歴史は終わることになる。
1990年に(株)ジーエフティよりG4、G12の再生産を依頼されることになり、トレバー、アイバーそしてトレバーの長男であるマークによりDARE(Design and Research Engineering)社が設立され、2年余の歳月をかけ、オリジナルの作り手によってG4、G12が復活した。
今でも当時の姿(中身は変更があっても)そのままに新車で手に入るクルマというのは数少ない存在と思われる。しかも、そういうクルマは何故かイギリスに多いというのは、恐らくバックヤードビルダーが生き残れる環境とリンクしていると考えられる。これこそがイギリスの特殊性であるとともに特徴なのだと思っているのだが、日本では到底考えられない状況だと思う。日本における標準化と差別化というのは一見すれば良いことのようだが、ジツのトコロ“枠に収まらないモノを淘汰する”作業だったように思えてならない。イギリスのバックヤードビルダーが温々と生存できているはずは勿論ないが、日本なら“瞬殺”状態に近いとすればどうなのだろう。
さて、この記事は2008年に書いたものを再編集したのだ。
わざわざこんな長い話をココに転載しようと思ったのは、企業戦略という側面からこういったことを描くのは意義が大きいと思われたからである。
この記事が書かれた当時「自動車趣味」の枠を越えて、零細企業の存続性や収支点など会社経営サイドの議論がブログ内で交わされるキッカケとなった。
経営というのは魅力ある商品があることは勿論だが、それだけでは成り立たない。製造業と小売業でも経営の収支分岐点は異なるし、黒字であってもキャッシュフローの悪化から倒産することもあり得る。
そもそも製造業で原価率が50%以上なら、意味はほとんどない。
ハッキリ言うが赤字である。
もし原価率が50%以上なら赤字で、それ以外の資金を注入していることになる。
材料と同じだけ儲けを出しているじゃない、と思ったなら会社の経理を学び直すが良い。そう思った時点で君は経理に弱いかずさんだ。
また赤字でも良いというならば別の理由(動機)が必要なのだ。
珍しくハンドメイドのことに言及してみるのだが、このジネッタカーズというメーカーは究極のハンドメイドと言えるだろう。その中でヒットしたのはG4、G15の2車種のみであり、よく知られているG12ですら採算がいいモデルではなかった。
想像できると思うが、ジネッタカーズという会社が安泰で残ったわけでなく、買収されながら現在に至った意味を改めて考えるべきである。
クルマという趣味は今後も残るだろう。
だが、それが経営できる最大の理由とはならないのは、これらバックヤードビルダーの存続が雄弁に語っている。決して楽な道ではなく、今後もそれは変わらない。そんな苦しい道を選択できるのは「クルマに熱い情熱を注げた」からだと思う。それも簡単には変わらない情熱だ。
自動車という高額商品においてでさえビジネスが困難なことなのは忘れないで欲しい。あなたがやろう(やっている)のは自動車より更に採算性が悪いビジネスなのだ。
それでも私たちは食わなければならない、これも真実である。
単刀直入にいう。
自動車の話は「お門違い」なんかでは決してない。
ハンドメイドをする人も好む人も今後ブームに限らずずっといるだろう。しかし、それで食える人は限られる。
存続することと食えることは本質的に異なるものだ。
アマチュアバンドはたくさんあるが、その中でプロになるのはわずかでヒットして食えるようになるのはもっとに少ない。この方が解り易いかな。
そしてヒットして生き残れる方に入ると思える確信に裏付けなどあるはずもない。
あくまでビジネスと割り切るなら、運転資金が潤沢ではない個人は設備投資も含めてシビアでないと本当に生き残れない。どんぶり勘定など以ての外である。食いたいのにできないのなら「愚か者」であり、趣味ならばそれだけ収入があって生活が楽なのだ。そう思われても仕方がない。
これは人の世の常である。
さぁ、あなたはどんな選択をする。
そうジネッタだ。イギリスには数多くのバックヤードビルダーが存在しており、ロータスもかつてはそのひとつだった。ジネッタもそんなメーカーで、現在もバックヤードビルダーの要素を色濃く残したメーカーだ。


ジネッタの歴史は、1957年にイギリスのサーフォーク州で建築業を営んでいたクルマ好きのウォークレット四兄弟、ダグラス、トレバー、ボブ、アイバーによって、中古のウーズレイ・ホーネットを改造したG1というレーサーが作られたことによって始まる。このレーサーは彼等が地元のスネッタートン・サーキットをはじめ当時各地で行われていた草レースに出場するためのレーサーだった。しかし試運転の際、家を出たところでクラッシュしてスクラップになってしまう。
しかしこの事故が彼等に火をつけたのか、すぐに次のマシンの製作に取り掛かり完成させたG2は、25mm鋼管スペースフレームにフォードの1.1リッターエンジンを載せ、高い評価を得ることになる。
本来は彼等がレースに出るために製作されたレーサーだったが、近所のクルマ好き達に製作の注文を受けるのである。
ウォークレット兄弟は半完成品のキットカーとしてG2を156ポンドの値段で販売した。当事、イギリスでは自動車に50%もの物品税が掛けられていたが、キットカーはこの消費税が課税されなかったことから、キットカーは「どうしてもクルマを持ちたい、運転したい」と考えるクルマ好きの庶民に人気が高かった。このレーサーの成功がバックヤードビルダーとしての道を決定付け、彼等が自動車メーカーとして進む決心をさせる。つまり「ジネッタカーズ社」の誕生だ。
1960年にはG2の改良型でFRP製のボディーを採用したG3が登場、翌年の1961年にはジネッタの最大のヒット作であるジネッタG4がロンドン・レーシングカーショーでデビューする。
G4はラウンドチューブのスペースフレームにアイバーがデザインしたFRPのボディーを被せた小さなスポーツカーで、デビューと同時にサーキットにも姿を現し、話題を集める。
サスペンションはフロントが上下Aアームによるダブルウイッシュポーン+コイル。リヤはフォード・アングリアから流用したライブアクスルをトレーリングアームとAブラケットで固定+コイルというレイアウトで、重量は完成車で419Kgだった。ボディサイズは3350×1422×685(フロントウインドまで含めると923mm)ホイールベース2030mm、トレッドは前後共に1168mm。かなり小さい。
幅だけは広いが、まぁ昔の軽四並みの大きさで異常に低い車体を想像すればいいと思う。
G4には当初クライマックス750ccが搭載される予定だったが、このエンジンが多くのバックオーダーをかかえて入手が困難な為、しかたなくフォード・アングリアの105E・977cc・OHVエンジンが搭載される。
完成車は697ポンド、キットで499ポンドという価格で販売され、16ポンドのオプション料金でフォード109E・1340ccエンジンも選べた。
時を同じくしてウォークレット兄弟はそれまでの建築業を完全に廃業し、エセックスに工場を設立している。恐らく、このG4が成功すると確信していたのだろう。
さて当事のキットカーとはどんな内容だったのだろうか。G4では以下のような内容でオーナーの元に届けられていたようだ。
1エンジンとスプリング、ショックまでが組まれた完成シャシー
2インパネとメーター類
3スイッチ類、シート
4オースチン・スプライトから流用したフロントガラス
5ホイール、タイヤ5個
6ボディパネル
何となく「ラジコン」を連想した。
この内容ならやる気と場所さえあれば作れそうだ。クルマも小さいので、さほど場所は取らなかっただろう。「小さく軽い」のはキットカーでは個人が趣味で作る裏庭サイズとして必須だったと思われる。
2年後の1963年、G4は多くの部分に改良を受けシリーズ2へと発展する。
フレームはチューブラーパイプからスクウェアパイプで構成されるようになり、エンジンペイのサイドシルが下げられフロントサスペンションもウイッシユポーンのロアアームのピポット位置を16mmずつ外側に出しスプリングのストロークを増している。フロントディスクブレーキの採用もこの時からだ。
最も変更を受けたのはボディーで、リヤのテールフィンを廃止し、いわゆるスラブタイプと呼ばれる、絞り込んだリヤスタイルとなりトランクルームが拡大される(全長は3547mmに伸びる)
多分、日本で一番有名なボディーがこのモデルだ。
そして、合わせガラスのフロントウインドとパースペックスと呼ばれる樹脂製のサイド・リヤウインドを持つ脱着可能なハードトップもオプションで用意された。因みにG4にはドアノブがない。オープンモデルは問題ないが、ハードトップではサイドのウインドウに開けられた穴から腕を突っ込み手探りで内側のリリースハンドルを探るワケだ。知らない人はどうやってドアを開けるかすらわからない(笑)
まだエンジンは基本的に997ccのフォード105Eだった。というのも、当時の国際レース規定で市販車部門は同一エンジンを登載したクルマが100台以上作られていることと定められていたからだ。そして、9月にようやくG4は100台以上の生産によるホモロゲーションが認められる。その後、エンジンのラインナップも増やされフォード113E/1198cc、116E/1498ccエンジンも選択できるようになるのだ。ちなみに116Eを積んだモデルは、当初G5と名付けられ発売されたが、市場ではG4のハイパワー版と受けとめられ、G5の名前が全く定着せず、結局メーカー自らG4-1500とモデル名を変えた経緯がある。まぁ東京ドームの“ビッグエッグ”も定着しなかったしね(笑)
この時期、更に本人の希望に応じてコルチナの112Eやロータスツインカムも選択できるようになる。
そして64年に登場した、G4シリーズ2をベースにリヤのサスペンションをフロントと同じダブルウイシュボーンに変え、4輪独立とし4輪ディスクプレーキを採用したG4Rというレーシングモデルがある。
今回見掛けたG4はこのG4Rだ。

当時、草レースに参加していたドライバー達から同じ105Eを載むロータスセプンよりも戦闘力が高いと評判だった。
G4・G4Rはこの後、イギリス国内レースで多くの戦債を残している。
特に64年はそのピークと言え、ワークスドライバーのクリス・ミークは自分で組み立てたG4にコスワースのカムシャフトを組み込んだフォード製1650ccのOHVエンジンを搭載し、lシーズンに8回の優勝・6回の2位を獲得するなどの戦績を収めている。更にG1のころからホームグラウンドであったスネッタートン・サーキットでは2000cc・180馬力のポルシェ904が樹立したコースレコードもあっさりと塗り替えてしまっている。
レースでの戦績はすぐに人々の話題となり、市販車も順調に販売を伸ばした。当時のイギリスをはじめヨーロッパではレースの戦績が市販車の販売に大きく影響していた。それはワリと最近までの傾向のようだ。例えばAlfa Romeo155も最初は全く売れなかったが、DTMやBTCCで活躍をはじめた途端売れるようになっている。
G4も最終的に500台以上の生産が記録されている。この成功によりジネッタカーズ社は経営安定の基盤を築くことができた。
G4はエンジンやシャシーを改良しながら様々なバリエーションが発売されている。

1966年、いよいよG4に代わるレーサーとしてG12を市場に送りだす。
G12は純粋にサーキットレースでの使用を目的として開発され、G4と共通なのはフロントスタイルと鋼管フレームにFRPボディーを被せている事くらいで中身はまったくの別物。ミッドシップ・レイアウトを採用したボディサイズは3500×1550mm×1050mmとG4にくらべ若干大きくなった。
サスペンションはフロントがトライアンフスピットファイアから流用したダブルウイッシユポーン/コイルにスタビライザー。リヤは長いダブルラジアスアームで位置決めされた逆A型ロアウイッシュボーンとトランスバーリンク/コイルにアジャスタブルスタビライザーを採用した独立懸架を採用。ブレーキもスピットファイアから流用したガーリング製4輪ディスクが奢られている。流用とはいえ、スピットファイアは車体重量が800kgに対してG12は560kgで240kgも軽いから十分な制動力だった。ドライバーの背後に完全にミッドシップで縦置きされたエンジンは、相変わらずG4と同じ105E(39PS/5000rpm)が標準だったが、実際のレースではG12はスペシャルGTクラス/1150cc以下にエントリーされるのでコスワースSCAというフォード105Eをベースに5ベアリング&SOHC化したフォーミュラー2用エンジン(115PS/8750rpm)を搭載するのがほとんどだったという。
ミッションはヒューランドMk-4の5速にLSDを組み合わせ、67年からは1498ccのロータスツインカムをチューンした1594ccのコスワースMk-8が搭載されている。
G12は9月のシルバーストーンのデビュー戦でワークスドライバーのウイリー・グリーンによってラップレコードを記録。続いてホームグランドのスネッタートンではクラス優勝を果たす。
また翌年にはブランズハッチで7リッターのシェルビー・コブラ、4・7リッターフォードGT40という強敵を打ち破るなど数々の輝かしい戦績を収め、以降、ロータスエラン、TVRといった上級クラスのクルマを相手に活躍し1150cc以下クラスでは無敵を誇った。
レースに出場し勝つ事を命題とされたG12は、キットカーではなくコンプリートカーだけが販売され、その価格は1200ポンドだった。オリジナルのG12は50台弱の生産が記録されている。
しかし、純粋にサーキットを走るために生を受けたG12は公道を走るにはあまりにスパルタン過ぎていた。特に複雑なシャシーは手間とコストが嵩み生産性を大きく損なっていた。実のところ、ロータスもスーパーセブンシリーズで同じジレンマに陥っていた。それがスーパーセブンの販売停止という事態に繋がったのだが、ライバルであるジネッタも同様だったとは何とも奇遇な現象である。
こういった反省から、企業としてもっと生産性の高いスポーツカーを作るべきだ、として登場したのがG15である。生産台数は800台を数え、後にも先にもこれを超えるヒット作は生まれなかった。
G4は67年によりラグジュアリーに振ったモデルを登場させるが、市場からの反応はイマイチで69年に生産を終了する。
68年にはG12の発展型であるG16が登場したことで実質的にG12の歴史は終わることになる。
1990年に(株)ジーエフティよりG4、G12の再生産を依頼されることになり、トレバー、アイバーそしてトレバーの長男であるマークによりDARE(Design and Research Engineering)社が設立され、2年余の歳月をかけ、オリジナルの作り手によってG4、G12が復活した。
今でも当時の姿(中身は変更があっても)そのままに新車で手に入るクルマというのは数少ない存在と思われる。しかも、そういうクルマは何故かイギリスに多いというのは、恐らくバックヤードビルダーが生き残れる環境とリンクしていると考えられる。これこそがイギリスの特殊性であるとともに特徴なのだと思っているのだが、日本では到底考えられない状況だと思う。日本における標準化と差別化というのは一見すれば良いことのようだが、ジツのトコロ“枠に収まらないモノを淘汰する”作業だったように思えてならない。イギリスのバックヤードビルダーが温々と生存できているはずは勿論ないが、日本なら“瞬殺”状態に近いとすればどうなのだろう。
さて、この記事は2008年に書いたものを再編集したのだ。
わざわざこんな長い話をココに転載しようと思ったのは、企業戦略という側面からこういったことを描くのは意義が大きいと思われたからである。
この記事が書かれた当時「自動車趣味」の枠を越えて、零細企業の存続性や収支点など会社経営サイドの議論がブログ内で交わされるキッカケとなった。
経営というのは魅力ある商品があることは勿論だが、それだけでは成り立たない。製造業と小売業でも経営の収支分岐点は異なるし、黒字であってもキャッシュフローの悪化から倒産することもあり得る。
そもそも製造業で原価率が50%以上なら、意味はほとんどない。
ハッキリ言うが赤字である。
もし原価率が50%以上なら赤字で、それ以外の資金を注入していることになる。
材料と同じだけ儲けを出しているじゃない、と思ったなら会社の経理を学び直すが良い。そう思った時点で君は経理に弱いかずさんだ。
また赤字でも良いというならば別の理由(動機)が必要なのだ。
珍しくハンドメイドのことに言及してみるのだが、このジネッタカーズというメーカーは究極のハンドメイドと言えるだろう。その中でヒットしたのはG4、G15の2車種のみであり、よく知られているG12ですら採算がいいモデルではなかった。
想像できると思うが、ジネッタカーズという会社が安泰で残ったわけでなく、買収されながら現在に至った意味を改めて考えるべきである。
クルマという趣味は今後も残るだろう。
だが、それが経営できる最大の理由とはならないのは、これらバックヤードビルダーの存続が雄弁に語っている。決して楽な道ではなく、今後もそれは変わらない。そんな苦しい道を選択できるのは「クルマに熱い情熱を注げた」からだと思う。それも簡単には変わらない情熱だ。
自動車という高額商品においてでさえビジネスが困難なことなのは忘れないで欲しい。あなたがやろう(やっている)のは自動車より更に採算性が悪いビジネスなのだ。
それでも私たちは食わなければならない、これも真実である。
単刀直入にいう。
自動車の話は「お門違い」なんかでは決してない。
ハンドメイドをする人も好む人も今後ブームに限らずずっといるだろう。しかし、それで食える人は限られる。
存続することと食えることは本質的に異なるものだ。
アマチュアバンドはたくさんあるが、その中でプロになるのはわずかでヒットして食えるようになるのはもっとに少ない。この方が解り易いかな。
そしてヒットして生き残れる方に入ると思える確信に裏付けなどあるはずもない。
あくまでビジネスと割り切るなら、運転資金が潤沢ではない個人は設備投資も含めてシビアでないと本当に生き残れない。どんぶり勘定など以ての外である。食いたいのにできないのなら「愚か者」であり、趣味ならばそれだけ収入があって生活が楽なのだ。そう思われても仕方がない。
これは人の世の常である。
さぁ、あなたはどんな選択をする。
Posted by *clear* at 11:51│Comments(0)
│ハンドメイド(IKEA)