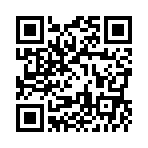2011年06月22日
ビギナーに向けた木工Tips1
今から木工を始めよう、というビギナーから質問されることはこの記事で書いた。
去年の夏休みに行った「親子木工教室」でも扱った教材以外に様々な質問が飛び出し、多くの方が木工というブラックボックスの中身を見てみたい、知りたい、あるいは分からない、という印象を持った。
そこで今回から超初心者の新たな木工人へ向けて基礎中の基礎、というテキストを記述しようと考えた。
参照にしている記事には「道具を持たない」という究極の選択が書かれているが、いかんせん、ホームセンターの工作室が広いとは限らない。1組でキャパシティー一杯の場合もあるし、何組もの作業者を受け入れられるところもあるだろう。
従い、待ち時間を避け自宅でも行いたい、という方に向けて道具も含めたテキストにすることにした。
特に電動工具はコストパフォーマンスを重視した解説を試みていくので参考にしていただきたい。
まず木工を始めるに当たって何が重要なのか。その辺りから話を始めてみたい。
木工総論
文字通り木を加工することから木工となる。このことが簡単であり難しい問題なのだ、と言わねばならない。
木という素材が金属に比較して柔らかいという特性がある。
切断するにしても削るにしても金属より容易だからこそ、ビギナーが木工を始めたりご主人が日曜大工になったりするのである。
しかし、突き詰めていくと自然素材であるが故に難しい問題が出てくる。
材料の全てが均一ではない、という問題だ。この事によって木の繊維の方向を読んだり、将来的にどの程度狂いが出るのか読まなくてはならなくなる。プロのプロたる所以は、長い経験によってそれを容易に見抜けることだろう。
大工は「木に習う」とよく言う。それはその材料の質を見抜き、加工を木に合わせろという意味だ。
しかし初心者がそういう風になるには年月を必要とするし、何より仕事で毎日携わっているプロと同等のレベルになるのは土台ムリな話だ。週に48時間以上木と向き合うプロに、週末に数時間木工を行うアマチュアが追い付くには、相当な努力と勉強が必要なのは火を見るまでもない。
そこで僕がビギナーに向けたメッセージは、あくまで「アマチュアイズムのある木工」を目指そう、というものだ。
プロは仕事だから辛いことにも耐えられるが、趣味ではそれは楽しくない。
結果的に自己満足になるかも知れないが、売る事を目的にしたものではないのだから社会に対する販売者の責任がない、というだけで気が楽だ。逆に出来が良ければ「家族からの評価が上がる」ことだって考えられる。まずは気軽に始められるところからやってみてはどうだろうか。
さて、ではどのようなところから始めれば良いのだろう。
そこで僕は「箱物」を提案したい。
ただの四角い箱を組むところから木工の基礎は始まる。最も簡単で、誰もが考え付く木工品だが、侮る事なかれ。これができないと高度なものには行けない、というほど木工の基礎が凝縮されている。
もし、これが上手くできたのなら、あなたには工作と加工のセンスがある証である。
箱物をしっかり製作する上で重要なのは、各材料が接合される部分の直角である。
これを「矩(カネ)を出す」と大工は呼ぶ。
矩とは直角のことだ。これは建築現場でも頻繁に職人たちが口にする。
木工の基礎は如何にその直角を正確に出すかに尽きる。
では、どうやったら直角が正確に出るのであろう。
直角にならない原因から考えると理解できる。
1 材料が反っていたり捩れていたり狂いが大きい
2 切断面が直角に切れていない
3 対面にある材料の長さが異なっている
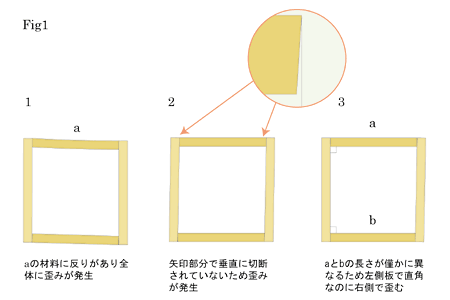
Fig1では理解しやすいよう、単純に正面から見た各部の直角について示した。実際には奥行き方向への直角も加わってくる。
上記の3点のどれかが当て嵌まると、どんなに正確に組もうとしても箱が歪んでくる。
このことからわかるのは、良い作品を制作するには、まず材料選びの段階からスタートしているということだ。
材料の狂い(暴れるともいう)を修正する機械やテクニックを持たない者にとって重要なのは、そのような修正が必要のない素直な材料をセレクトすることであり、実はプロも歩留まりの理由から反りの大きい材料を避ける傾向にある。これは非常に重要なのでぜひ念頭に置いて欲しい。
今回、この箱物に使用する材料はSPFという材料を使用する。
この材料については一度記事として取り上げているので一読されたい。
8.8mmの幸せ。
1×4(19×89mm)の6フィート材が教材になる。
安価、ということもあるが比較的柔らかく加工が楽で、初心者向きだからだ。
Tips2では材料選びから始めたいと思う。
<追記>
金の手、と時に表記される「矩(かね)」だが、矩という字に垂直や直角という意味がある。
非常に古い言葉だそうだ。
今後詳しく解説する予定だが、大工の日常的な計測道具に「差し金」がある。この差し金は他に「曲尺」や「矩尺」などと多くの当て字があるが、この2つの漢字読みは差し金の特徴を良く表している。
つまり、差し金が長さを測る以外に直角に折れていることから、直角の確認や、ある面に対して垂直に墨付けするための道具だ、ということである。
また差し金が日本に入ってきたのは非常に古い時代だとされていることから、古語である「矩」が用いられたのだろう。「金」の字が用いられるのは後の時代と思われる。推測だが言い伝えによって技術が伝承される、つまり書物に依らない伝承のために話し言葉から「金の手」に転じたことはあり得る。
因みに家を建てられた方も多いと思われるが、普通は1/100平面図とパースはご覧になると思うが、矩計図まで見るケースは滅多にないと思う。矩計図は「かなばかりず」と読む。簡単に言うとその建物で重要な部分を描いた詳細断面図のことだ。一般的な住宅なら1/50平面図と矩計図だけで建てられる、というほどだが、それだけに重要な図面なのである。
この図面名にも矩の字が使われている。これはGL(地盤基準面)やFL(床基準面)から垂直方向、すなわち高さを示す図面であり、このことからも矩とは直角を示す漢字であることがわかる。
さて、差し金には様々な使い方があり、それだけでもかなりの解説が必要だが、今回はこの作品を製作するに当たって必要なテクニックを解説するに止める予定である。
去年の夏休みに行った「親子木工教室」でも扱った教材以外に様々な質問が飛び出し、多くの方が木工というブラックボックスの中身を見てみたい、知りたい、あるいは分からない、という印象を持った。
そこで今回から超初心者の新たな木工人へ向けて基礎中の基礎、というテキストを記述しようと考えた。
参照にしている記事には「道具を持たない」という究極の選択が書かれているが、いかんせん、ホームセンターの工作室が広いとは限らない。1組でキャパシティー一杯の場合もあるし、何組もの作業者を受け入れられるところもあるだろう。
従い、待ち時間を避け自宅でも行いたい、という方に向けて道具も含めたテキストにすることにした。
特に電動工具はコストパフォーマンスを重視した解説を試みていくので参考にしていただきたい。
まず木工を始めるに当たって何が重要なのか。その辺りから話を始めてみたい。
木工総論
文字通り木を加工することから木工となる。このことが簡単であり難しい問題なのだ、と言わねばならない。
木という素材が金属に比較して柔らかいという特性がある。
切断するにしても削るにしても金属より容易だからこそ、ビギナーが木工を始めたりご主人が日曜大工になったりするのである。
しかし、突き詰めていくと自然素材であるが故に難しい問題が出てくる。
材料の全てが均一ではない、という問題だ。この事によって木の繊維の方向を読んだり、将来的にどの程度狂いが出るのか読まなくてはならなくなる。プロのプロたる所以は、長い経験によってそれを容易に見抜けることだろう。
大工は「木に習う」とよく言う。それはその材料の質を見抜き、加工を木に合わせろという意味だ。
しかし初心者がそういう風になるには年月を必要とするし、何より仕事で毎日携わっているプロと同等のレベルになるのは土台ムリな話だ。週に48時間以上木と向き合うプロに、週末に数時間木工を行うアマチュアが追い付くには、相当な努力と勉強が必要なのは火を見るまでもない。
そこで僕がビギナーに向けたメッセージは、あくまで「アマチュアイズムのある木工」を目指そう、というものだ。
プロは仕事だから辛いことにも耐えられるが、趣味ではそれは楽しくない。
結果的に自己満足になるかも知れないが、売る事を目的にしたものではないのだから社会に対する販売者の責任がない、というだけで気が楽だ。逆に出来が良ければ「家族からの評価が上がる」ことだって考えられる。まずは気軽に始められるところからやってみてはどうだろうか。
さて、ではどのようなところから始めれば良いのだろう。
そこで僕は「箱物」を提案したい。
ただの四角い箱を組むところから木工の基礎は始まる。最も簡単で、誰もが考え付く木工品だが、侮る事なかれ。これができないと高度なものには行けない、というほど木工の基礎が凝縮されている。
もし、これが上手くできたのなら、あなたには工作と加工のセンスがある証である。
箱物をしっかり製作する上で重要なのは、各材料が接合される部分の直角である。
これを「矩(カネ)を出す」と大工は呼ぶ。
矩とは直角のことだ。これは建築現場でも頻繁に職人たちが口にする。
木工の基礎は如何にその直角を正確に出すかに尽きる。
では、どうやったら直角が正確に出るのであろう。
直角にならない原因から考えると理解できる。
1 材料が反っていたり捩れていたり狂いが大きい
2 切断面が直角に切れていない
3 対面にある材料の長さが異なっている
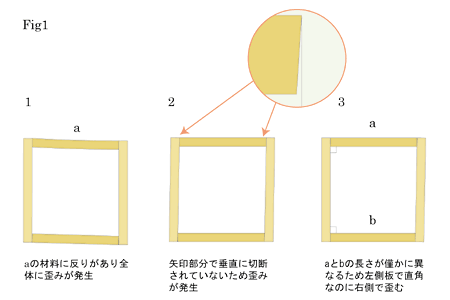
Fig1では理解しやすいよう、単純に正面から見た各部の直角について示した。実際には奥行き方向への直角も加わってくる。
上記の3点のどれかが当て嵌まると、どんなに正確に組もうとしても箱が歪んでくる。
このことからわかるのは、良い作品を制作するには、まず材料選びの段階からスタートしているということだ。
材料の狂い(暴れるともいう)を修正する機械やテクニックを持たない者にとって重要なのは、そのような修正が必要のない素直な材料をセレクトすることであり、実はプロも歩留まりの理由から反りの大きい材料を避ける傾向にある。これは非常に重要なのでぜひ念頭に置いて欲しい。
今回、この箱物に使用する材料はSPFという材料を使用する。
この材料については一度記事として取り上げているので一読されたい。
8.8mmの幸せ。
1×4(19×89mm)の6フィート材が教材になる。
安価、ということもあるが比較的柔らかく加工が楽で、初心者向きだからだ。
Tips2では材料選びから始めたいと思う。
<追記>
金の手、と時に表記される「矩(かね)」だが、矩という字に垂直や直角という意味がある。
非常に古い言葉だそうだ。
今後詳しく解説する予定だが、大工の日常的な計測道具に「差し金」がある。この差し金は他に「曲尺」や「矩尺」などと多くの当て字があるが、この2つの漢字読みは差し金の特徴を良く表している。
つまり、差し金が長さを測る以外に直角に折れていることから、直角の確認や、ある面に対して垂直に墨付けするための道具だ、ということである。
また差し金が日本に入ってきたのは非常に古い時代だとされていることから、古語である「矩」が用いられたのだろう。「金」の字が用いられるのは後の時代と思われる。推測だが言い伝えによって技術が伝承される、つまり書物に依らない伝承のために話し言葉から「金の手」に転じたことはあり得る。
因みに家を建てられた方も多いと思われるが、普通は1/100平面図とパースはご覧になると思うが、矩計図まで見るケースは滅多にないと思う。矩計図は「かなばかりず」と読む。簡単に言うとその建物で重要な部分を描いた詳細断面図のことだ。一般的な住宅なら1/50平面図と矩計図だけで建てられる、というほどだが、それだけに重要な図面なのである。
この図面名にも矩の字が使われている。これはGL(地盤基準面)やFL(床基準面)から垂直方向、すなわち高さを示す図面であり、このことからも矩とは直角を示す漢字であることがわかる。
さて、差し金には様々な使い方があり、それだけでもかなりの解説が必要だが、今回はこの作品を製作するに当たって必要なテクニックを解説するに止める予定である。
Posted by *clear* at 14:22│Comments(0)
│Wood Workshop